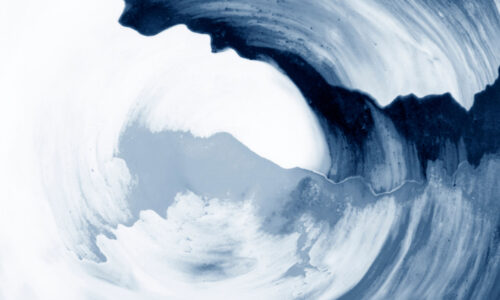
吉本ばなな連載『和みの想い出』第1回
2020.02.14 COLUMN
もういただいてからずいぶん経ってしまった箱のままの日本茶を、長い間捨てることも開けることもできずにいた。
私にとってもうひとりの母であった、母の若い頃からの親友だったあっこおばちゃんが毎年送っていてくれたお茶の最後の1缶だったからだ。
彼女は若い頃母と同じ病院で結核の手術をしてたいへんな思いをし、もう病院はいやだといって、最後の最後まで家でじっと痛みに耐えて亡くなった。
私の母の形見のカーディガンをなるべく着ないでいるの、匂いが消えちゃう気がして、と言いながら。
西武池袋線沿線の埼玉県に住んでいたあっこおばちゃんは、駅までバスに乗って、駅前の大きなデパートのお茶売り場で毎年お茶を選んで送ってくれていた。
今の時代は日本中いや世界中のあらゆるお茶をネットで注文できる。
でも彼女にとって、大切な私に送るお茶は自分の足で1時間くらいかけてお店にたどりつき、試飲をして、自分で伝票に住所を記入して送るものだった。あの時代の手間とか愛情とか時間の使い方を、もう私の体はすっかり忘れてしまった。
いつも新茶の季節になると留守番電話にながながと、おっとりした高い声の、優しい口調のメッセージが入っていた。
「今年はね、飲んでみたけれど狭山茶よりも宇治のお茶のほうがおいしく感じたので、そちらを送りました。埼玉に住んでいるのに変ですね。よかったら飲んでみてね」
かけなおすと彼女は、全く同じ内容をもう1回説明してくれる。
数回しか会っていない私の夫や子どもの名前を、彼女は最後まで間違えることはなかった。
あっこおばちゃんが亡くなって、初めて彼女が母の形見を身につけなかった気持ちがわかった。
最後に送ってもらったお茶を飲み終わってしまったら、彼女の死がほんとうになってしまう。すでに両親を亡くしている私の赤ちゃんの時代を知っている存在がほんとうにいなくなってしまう。
それで開けられずにいた。
しかし、そんなことを言っている間に、自分が明日どうなるかわからない年齢になってきてしまった。
私は昨年の大掃除のときに、そっとその缶を開けてみた。銀色の真空パックに包まれたお茶は多少香りが落ちているのかもしれないが、まだまだ鮮やかな緑色を保ち、飲める状態だった。
お湯を注いでゆっくりと飲むと、時間の流れなんてなかったかのようにきれいな苦味といい香りがよみがえった。
ちゃんと区切りをつけるのにずいぶん時間がかかってしまったな、と私は思った。
私にも時間が必要だった。ふだんの生活の中にいない人だったから、今も埼玉の空の下で生きているような気がしていた。でももう二度とお茶は送られてこない。それが現実だった。
もう中年過ぎた私の、「ほっぺたに触らせて」というのが彼女の最後の言葉だった。そんなことを味わいながらお茶を飲むことは、人にとって儀式なんだとそのときほど強く思ったことはなかった。
吉本ばなな
1964年東京都出身。1987年『キッチン』で海燕新人文学賞を受賞し作家デビューを果たすと、以後数々のヒット作を発表。諸作品は海外30数ヶ国以上で翻訳、出版されており、国内に留まらず海外からも高い人気を集めている。近著に『切なくそして幸せな、タピオカの夢』『吹上奇譚 第二話 どんぶり』など。noteにて配信中のメルマガ「どくだみちゃんとふしばな」をまとめた文庫本も発売中。
note.com/d_f (note)
twitter.com/y_banana (Twitter)

2024.10.04 INTERVIEWCHAGOCORO TALK

2025.01.10 INTERVIEW日本茶、再発見

2024.05.24 INTERVIEW茶と器

2021.07.13 INTERVIEW茶と器

2021.07.16 INTERVIEW茶と器

2021.11.23 INTERVIEW茶のつくり手たち

内容:フルセット(グラス3種、急須、茶漉し)
タイプ:茶器

内容:スリーブ×1種(素材 ポリエステル 100%)
タイプ:カスタムツール