
記事の前編はこちらRead Previous Page
福岡[万 yorozu]徳淵卓さん 特別インタビュー<前編>心を汲む、時間に寄り添う
福岡市の繁華街・天神から、歩いて20分ほど。赤坂エリアは、地元の人に聞いてみてもやはり、落ち着いた品のある地域と認識されているようだ。赤坂駅(天神駅のお隣りだ)を出て西へと進むと舞鶴公園が見えてくる。黒田長政ゆかりの福岡…
2025.03.21 INTERVIEW日本茶、再発見
福岡市中央区赤坂。古代日本において福岡が大陸との玄関口であったことを知らせる鴻臚館跡のほど近くで、2012年からお茶の時間を提供してきた[万 yorozu]。「裏方でありたい」と話す代表の徳淵卓さんではあるが、その経歴はやはり気になるところ。後半ではまず日本茶との出会いについて教えてもらった。
「恥ずかしながらデザインの学校を中退し、始めたのがバーテンダーの仕事でした」
今も日本トップバーの呼び声高い銀座[テンダー]のオーナーバーテンダー 上田和男さんに憧れてニューヨークに追いかけて行くほどにその熱は高かったという。デザインを学んだことで培われていたコンセプトメイクやネーミングセンスは、創作カクテルを生み出すことにも活かされ、コンペ入賞という実績も残した。
現代における日本の文化創造をコンセプトに、目黒[八雲茶寮]など日本食・日本茶文化のあり方提案してきた「SIMPLICITY」の緒方慎一郎さんと出会ったのは、バーテンダーとして数年経験を積んだ20代はじめの頃。福岡市内で緒方さんがプロデュースするホテルのバーを任されることになった。
「そのとき私は、このワインやあのウイスキーを仕入れましょう、と意気揚々と語っていたのですが、ある日緒方氏から『日本の酒のことは語れないのか?』と問いただされ、しばらく理解するまでに時間を要しましたが、そうか!と気付かされましたね。やるべきことがそのとき決まったというような。日本のことを真剣に考えなければいけないと気づいたんです。バーテンダーとしては中途半端だったのかもしれないと。でも、カクテルコンペなどでたくさんの時間を経て学べていたからこそ、緒方氏にチャンスをもらえたと思うのでそれもプロセスの一部だと、ありがたく思っているんですけどね」
九州各地をはじめ日本各地の日本酒蔵、焼酎蔵を巡り、日本茶についても研究することになった。そのとき訪ねたのが福岡県八女市の星野村。八女伝統本玉露で有名な産地だ。自然仕立ての茶畑は、それまでイメージしていたかまぼこ型の畑とは全く違う。なんだこれは、と頭が混乱する思いだったという。
「そこでおばあちゃんたちがお茶を摘んでいて、茶木の育成方法や製法などを知りました。さらに覆いをかけたりとか、すごく時間と手間のかかることをやっていて、当時は純粋に驚きました。ひと通りお茶のつくり方がわかったところで、お茶を飲みましょうとなった。あの時のお茶が衝撃的だった。伝統本玉露。何時間も待って出てきた、その一滴がね。『ただ馥郁たる匂が食道から胃のなかへ沁み渡るのみである』という漱石の気持ちも理解できるというような。ただただ感動したことを今でも思い出します」



茶一滴による青天の霹靂のような目醒めではあるが、自らのルーツを振り返れば、祖父母や母は茶道や書道の習いがあり、うち(日本)はこんなに恵まれていたんだと、点と点がつながったということでもあった。
幼少期に佐賀の吉野ヶ里遺跡を見たことをはっきり覚えているのも、徳淵さんのルーツの一つと言えるのだろう。
「歴史が好きなのは昔からですね。まだ幼い頃にちょうど吉野ヶ里遺跡が発掘されて、小学4年生のときに叔父さんに連れられて行ったんです。学校では縄文・弥生時代のことを授業で習っていましたが、僕らの時代はインターネットではなくて本とか教科書の絵しかないんです。文章や絵で想像しながら勉強するんですけど、現地に行くと遺跡を実際に見ることができる。そのことが実体験でわかるようになる。それから歴史が好きになりました」
この「実体験」もまた、德淵さんが重要視する要素の一つといえる。つづいて、店の奥にある箱庭を望むソファー席へと案内され、そこで德淵さんが愛する古道具のいくつかを見せていただいた。


「たまに古い茶碗でお茶をお客様に提供したりするんですよ。それを知っているか知らないかで試しているわけではなくて。道具の持つエネルギーというか道具が持っている美しさや用の美が、言葉ではなくて、手にとって口に含んだ瞬間に伝わるかな、伝わってほしいなと。
初めてのお客様でも『この器とてもしっくりきますね』とか『この器ってどなたが作られたんですか』とか、そういった質問をしてくれるとすごく嬉しいんです。何かが伝わったんだなと。そのものが持つエネルギーとか、その時代の熱量とかが今にまで伝わってお茶を飲んでもらえる。それは僕の根暗な楽しみに近いですが。
道具は使ってなんぼだと思いますよ。日本のお茶に関わる道具というのは、美術館で観るだけではなくて、それをお茶会で使ったりすることもある。実際に手にとって使える文化は世界でも稀だと思うんです。
古いお道具や美術品を手にとって鑑賞していると、それを所持していた先人達の美意識を共有することができ、その方々と会話することはもうできないですが、道具を通して対話できているような感覚になる。このような一服の茶の体験がとても有意義であると思っています」

「海外にお茶を広める動きはありますが、やはり日本に来て、この空気と景色とが一つになっていないと、パーツだけで届く形になってしまいます。新茶の時期には、スタッフだけではなく海外からのゲストとともに産地に行くことにしています。その土地の空気を知る、水を知る。それによってお茶のことを説明できる。実体験、経験が相手に伝わるかどうかを大事にしています。道具も同じですが、伝わるのは情熱だと思います。熱量があるからこそ、そこに行きたい、それに触れたい、それを飲みたいと思わせる。そうした連鎖的なものを生んでいくためにも、やはり実体験からしか語れないことはたくさんあると思うし、それが一番大事。世界に伝えていくためには、実際に手で触れてみる、この体験こそが一番です」

「これは古唐津の茶碗です。古絵唐津といって、なんともいえない植物を描いているんですよ。抽象的で可愛らしいというか。この世界観って日本人が求める美しさの一つで、決してうまく描こうとはしない。安土桃山時代の茶碗。上から見ると栗に見えるので初秋に使ったりするんです」

「これも同じ古唐津です。向きを変えると、笑った口にも泣いている口にも見えて面白いでしょう。この形は、わざとこうしたと解釈する人もいるのですが、実は違うと考えています。
日本では、備前や信楽のような土っぽい焼き物が主流でした。でも大陸では磁器がすでに焼かれていて、色彩豊かな染め付けの器がたくさんありました。日本にはまだそのような技術はなく、磁器や染付は憧れだったと思います。安土桃山以降の日本は経済的に潤っていたので、明との貿易にてたくさん焼かせるわけです。
朝鮮半島からはこの時代、井戸茶碗や粉引といった朝鮮の茶碗が重宝され、文禄・慶長の役で豊臣秀吉が朝鮮へ攻めると、朝鮮の陶工たちが日本に入ってくる。彼らから登り窯の技術が伝わって、日本の陶磁に革命が起こります。一度に大量の器を焼くことができるようになったのです。
この茶碗の形というのは、窯の中にいっぱい敷き詰められ何かの拍子で曲がって焼かれたからなんだと思います。意図して作ったのではなく、激動する歴史的変化の中で残ったなんとも可愛らしい形。
約70年間だけ栄えた唐津焼の、時代の短さやその成立したプロセスに現代の茶人たちは魅了され、こんなひねくれた茶碗も『かわいいじゃん』ってなるのは、やはりアミニズム的な日本の風習的美意識=センスだと思うんです。茶室はアシンメトリー(非対称)。石材に苔が生えて良い染みがあったり、木材は自然そのままの風合いを残し、土壁に藁、花は野にあるよう生き生きとしたさま、そういった質素な自然の美意識を見出す。割れていても金継ぎで直したり。それは“素の人間らしさ”にも通じているような、欠点があるし、苦手なこともある、でもそこを曝け出すことが美しい。日本人の心ってそこにあると思うんです」

「僕自身、人間らしいところ、完璧じゃない、失敗したもの、自然体であるものに興味が湧く。いいもの作ろうとしたら失敗するじゃないですか。失敗こそ、その人にとってのプロセスで、結果なんてどうでもよく、その過程をこそ大切にしたいですよね」

「何か想いが共通する友人と過ごしているとき、こうした愛着のある道具と一緒に愉しむのが僕の癒しの時間です。これがキュンとするというか、ワクワクするというか。だから僕らは、やっぱりその人が好きなもの、興味があること、趣味に対して、その時間を豊かにしてもらいたいというのが原点。自分がプライベートでそう感じるので、お客様にもそう思ってもらいたいと心を汲む。これ(手元の器)の自意識を押し付けても、興味がなかったら誰もわからないんですよ。その人たちの楽しみを、お茶を通して見出していく、共有していく、ということが僕らの仕事かなと思います」

貴重な品々に触れさせていただく。德淵さんの語り口は常に道具に対する愛に溢れていて、素人の我々にとってそれは覚えるべき知識ではなく、忘れられない体験として身に染みる。過去から受け継がれてきたものを、実際に体験して、未来に伝える。前編でも語られた「過去・現在・未来」の話だ。話は尽きないが、最後にあらためて、これから日本茶に携わる人たちが大事にするべきものは何か、尋ねてみた。
「色々なアプローチの仕方があると思います。お茶は自由であっていいと思います。その人のやりたいようにやったほうが広がっていく。でも、もっと深いところに目を向けると、新しいと思われるようなことでも、先人達が残してきたお茶の世界にはすでにそれがあったりするんです。
お茶を汲む人が増えるのはいいこと。そういう人たちにも、偉大なる先人達が残してきたものに興味を持ってもらえたらいいなと思います。それを学びながら新しくしていく。学びに終わりはないですが、そこをできるだけ深く学んでいかないと残っていかないと思います。日本茶ブームで終わってしまう。僕らはブームをつくっているわけではないし、ブームで終わらせてはダメで。僕なんかが未来に残せるような大それたことはできないかもしれませんが、未来に生きる誰かのために茶を通した一欠片くらいの知恵の種は蒔いておきたいという想いを抱いています。先人達の努力の賜物でここまで茶は成り立っている。私たちはそれを、心を込めて取り扱わないといけません。生産者さんもそうですし、器ひとつとってもそうですし、心して扱わせていただかないと、次につながっていかないんじゃないかと思いますし、一番大切にしているところです」

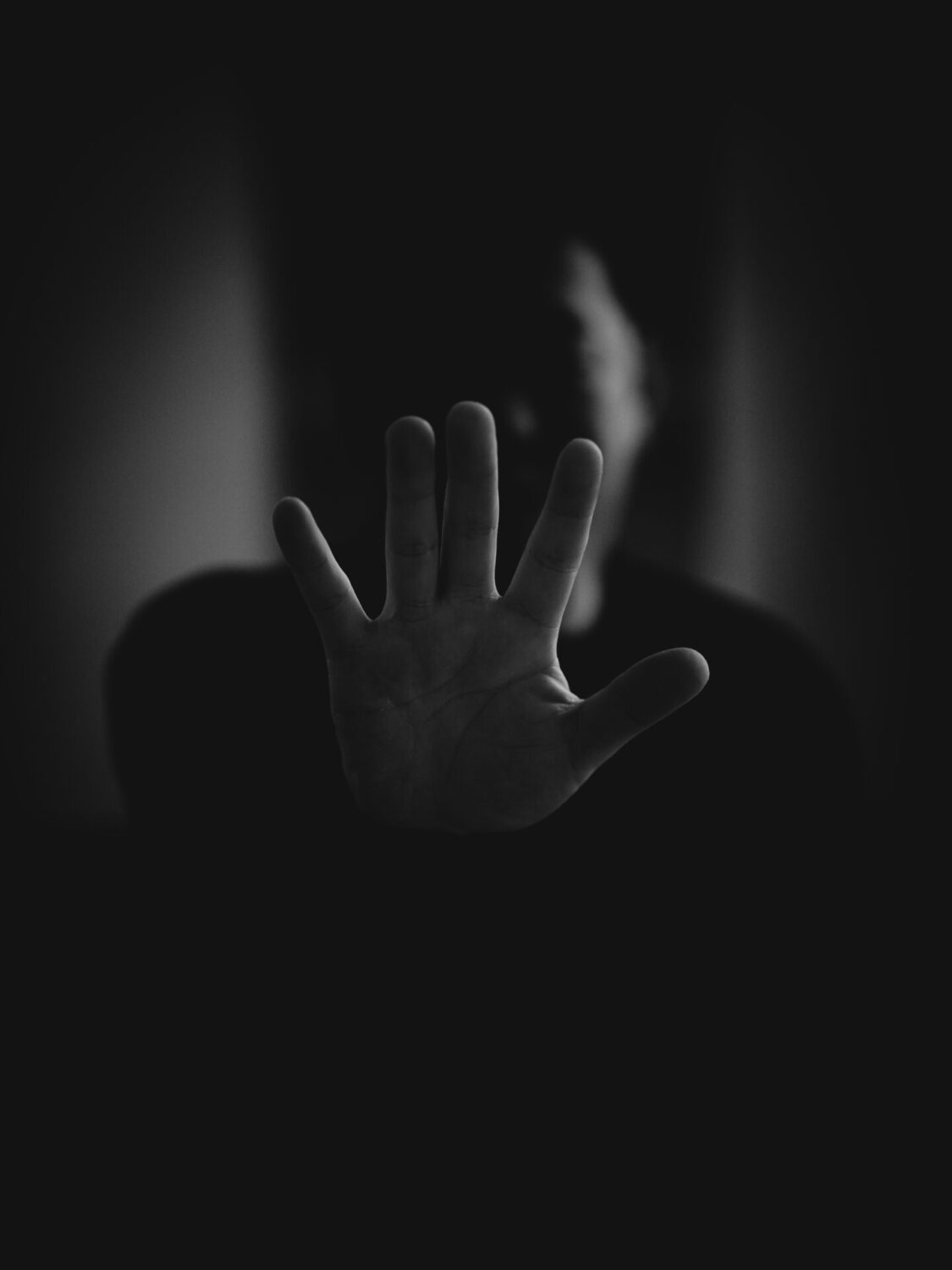
德淵 卓|Suguru Tokubuchi
株式会社万ヤ 代表取締役社長。[万 yorozu]茶司、茶方會 草司。1977年生まれ。バーテンダーとしてキャリアをスタートし、福岡市のホテルのフード&ビバレッジマネージャーを12年に渡り務めたのち、2012年、福岡県福岡市中央区赤坂にて[万 yorozu]を開業。2019年、イギリスの50 Bestによる新カテゴリー「World Best 50 discovery」に選出された。日本茶文化を各方面に伝える「茶方薈」の草司(理事)を務めるなど、文化発展のため多岐にわたる活動を行う。
IG @yorozu.suguru.tokubuchi
万 yorozu
福岡県福岡市中央区赤坂2-3-32
092-724-7880
12時〜24時、不定休
*予約優先につきお電話にて事前予約か当日お席確認のご連絡を。
yorozu-tea.jp
IG @yorozu.tea
Photo by Tameki Oshiro
Text by Yoshiki Tatezaki

2024.10.04 INTERVIEWCHAGOCORO TALK

2025.01.10 INTERVIEW日本茶、再発見

2024.05.24 INTERVIEW茶と器

2021.07.13 INTERVIEW茶と器

2021.07.16 INTERVIEW茶と器

2021.11.23 INTERVIEW茶のつくり手たち

内容:フルセット(グラス3種、急須、茶漉し)
タイプ:茶器

内容:スリーブ×1種(素材 ポリエステル 100%)
タイプ:カスタムツール